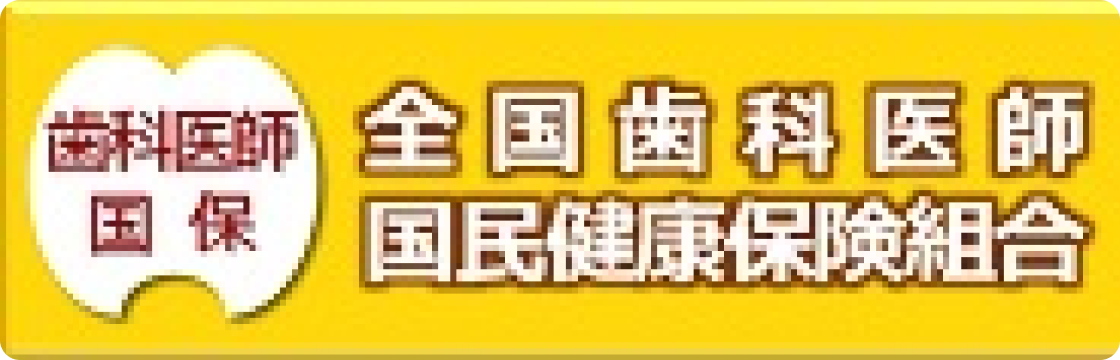食育について
「食育」について
子供達の教育というと、知育・徳育・体育ということがよく言われます。しかし最近、それだけでは足りないことが分かってきました。すなわち、人々が健全な心身を培い、豊かな人間性を育むためには「食育」という観点も必要だ、ということです。
では「食育」とは何でしょう。平成17年7月に施行された食育基本法では、基本法の目的や関係者の責務、基本計画の作成や基本的施策についての記述はありますが、「食育」の定義に関するものがありません。しかし、今までに出された種々の行政からの文書からまとめてみますと、食育とは『生きる上での基本であって、知育・徳育及び体育の基礎であり、様々な経験を通じて「食」に関する知識と「食」を選択する力を習得し、健全な食生活を実践することができる人間を育てること』であると言えます。
この中で述べられている「食」に関しては現在、以下のような現状と課題があります。すなわち、栄養の偏り、不規則な食事、肥満や生活習慣病の増加、過度の痩身志向、食の安全、食の海外への依存、伝統的食文化の危機等です。
戦後に国民の生活が欧米化し、食生活もそれに従って変化しました。欧米の食習慣が急速に導入された結果、多くの生活習慣病が発生しましたが、それだけではなく現代は栄養そのものの偏りも問題です。飽食の時代であるにもかかわらず、緑黄色野菜の摂取不足やカルシウムの摂取不足が存在します。
近年、生活時間が個人個人でバラバラになり、家庭生活に家族のまとまりが失われつつあります。食事時間も多様化し、子供が一人で食べる「孤食」「個食」が増加、朝食の欠食や就眠前の食事、その結果として家族団らんが失われて、コミュニケーションも減少しています。また、産業構造の変化が日本の一次産業を疲弊させ農産物の自給率は著しく低下、近年食の安全が問題視されています。
一方、食には生きるためという生物的意味だけではなく、食文化といわれる側面もあります。地域により食物の種類が違いますし、同一種であっても調理法が違うことがあります。そして、特別な時に特別な人々と特別な食事をする習慣が、地域により神事として保存されています。こうした食文化は伝統食として見直されていますが、栄養面からもその意義が解明されつつあるのです。スプーンを使うか、箸を使うか、大人数での大皿か、個人用の食器が用意されているか否か、こうした文化的側面も「食」にとっては大切なことです。「食育」ということは、食べものの種類や中味、調理法を教えることだけではなく、こうした文化的側面もしっかりと伝えていくことも大切な一面であることを忘れてはなりません。